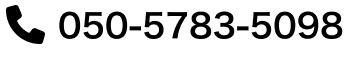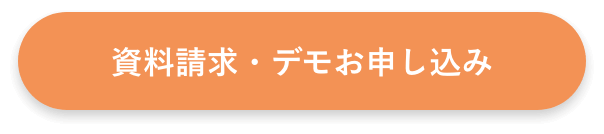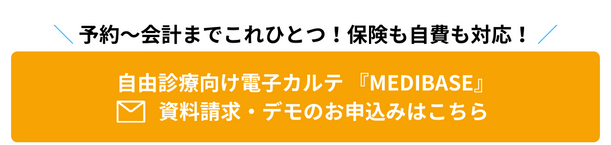カルテの整理方法は?保管期限や管理について
長い間、紙カルテの運用をしている病院やクリニック・診療所では、紙カルテの整理の方法、管理スペースの確保、保管方法などに悩みを抱えているでしょう。この記事では、カルテの保管期限や効果的な管理方法について解説しています。
記事の最後には、業界初の自由診療に特化したクラウド型電子カルテをご紹介します。カルテの整理にも有効なシステムです。ぜひ最後までご覧ください。
目次
紙カルテの整理の方法
クリニックにとって、多くの患者さんが病気の治療や健康管理などのために、自院を選択し受診をしてくれることはよろこばしいことです。
一方で、大変になるのは紙カルテの管理。診療科の治療の性質や、運営の長いクリニックや診療所であれば、長い付き合いの患者さんも多くなります。その分紙カルテの数もふえていくでしょう。
カルテの並べ方、順番など、日々のカルテ管理のルールを明確にしておかなければ、カルテを探すことになり、最悪の場合は紛失にもつながってしまう恐れがあります。
ここでは、紙カルテの管理の方法について紹介します。
ミドルデジット方式
ミドルデジット方式は、中間位桁番号とも言われます。基本的には患者番号を桁ごとに分けて整理することができます。その中間位桁、頭位桁、末位桁の順番に並べる方法です。もともと、0~9の数字にそれぞれ色が割り振られています。
この色の割り振りに沿って、一連の番号の100の位と10の位をカラー表示を同じ色の組み合わせにすれば中間位桁がまとまります。カルテを収納するとき、探すときには、まず該当する部分を同じ色の組み合わせ部分を見て、頭位桁、末位桁の順に見れば、該当するカルテにたどり着くことができます。
ターミルデジット方式
ターミナルデジット方式ではカルテファイルが10,000枚以上になる場合に便利です。
こちらもミドルデジット方式同様、基本的には患者番号を桁ごとに分けています。異なるのは位を並べる順番です。
ターミナルデジット方式では、末位桁、中間位桁、頭位桁の順番に並べます。0~9の数字にそれぞれ割り振られた色に沿って、一連の番号の10の位、1の位の2桁をカラー表示しています。同じ色の組み合わせ部分をまとめることで、末位桁がひとまとまりになります。
カルテの出し入れ時には、まず該当する番号と同じ色の組み合わせを探し、その後、中間位桁、頭位桁の順に見ていけば、必要なカルテを見つけることができます。
氏名カラー方式
氏名カラー方式は、患者さんの氏名をカラーコード化します。
「あかさたなはまやらわ」それぞれの1文字に色が割り振られています。さらに1~5までの数字にも色を割り振っています。これらの2つの要素の色の組み合わせで整理する方法です。
ア1、ア2、ア3…ワ1を左から順番に並べていきます。ア1は「あ」から始める名前の患者さん、ナ2は「に」から始まる名前の患者さんとなります。
背表紙の色で50音を分類するので、患者さんのお名前を元にカルテを見つけることが可能です。背表紙には患者さんのお名前も書かれているので、番号と名前を同時に確認することも可能です。ローマ字を用いた整理方法もあります。
紙カルテの保管方法
厚生労働省の医療施設調査によると、2017年時点の電子カルテ普及率は、400床以上の病院では85.4%です。一方、一般診療所は41.6%、200床未満の病院で37%と、小規模医療施設での電子カルテ普及率は低い状態が続いています。
このため、紙カルテの保管でお悩みのクリニックや診療所も少なくないでしょう。
ここでは、紙カルテの保管方法について解説します。
院内・施設内で保管する
開業して間もない頃や、それほど年数が経過していない場合は、カルテの保管もスムーズであることが予測されます。多くの患者さんが一定の期間で通院されるのであれば、受付近くでの保管もできるくらいの量でしょう。
しかし、年数が経つと患者さんの人数とともにカルテが増えてきます。こういった場合、普段の使用率が低くなったカルテは、別の場所に保管することを検討しなければなりません。
このような場合、病院やクリニックの建物内のカルテ庫など、院内で別の保管する方法があります。これは正統派と言える保管方法の1つ。一定のルールを設け、受付から距離のある場所で保管することも可能です。院内に活用できる空きスペースがあれば良いですが、なければ増設してスペース確保を検討しなければならない場合もあるでしょう。
外部倉庫で保管する
増加したカルテの保管法として、院内・施設内での空きスペースの利用や施設増設の検討についてご紹介しました。しかし、敷地の広さなど状況や条件によって、そのような方法を選択できないクリニックもあるでしょう。
そんな時には書類保管の専門業者外部倉庫での保管も選択肢の1つです。以前は、紙カルテは作成した自院で責任を持って保管することが求められましたが、厚生労働省により「診療録等の保存を行う場所について」が発出され、基準を達すれば外部でカルテ保存が可能になっています。
ただし、外部の倉庫となると手軽に出し入れができなくなります。このため、外部倉庫に保管するカルテは、直近での利用が全くない、保管期限を過ぎた、あるいは過ぎそうなカルテの保管向きだと言えるでしょう。
電子データ化し、保管する
紙のカルテはかさばってしまうため、患者さんが増えると紙カルテが増え、保管スペースの確保が困難になります。そこで紙カルテの電子化という方法が検討されます。
とはいっても、スキャンやPDF化すれば良いという単純なものではありません。
厚生労働省から出されている「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」においては、e-文書法を順守するための具体的な指針が示されており、これに従わなければなりません。
紙カルテの電子化に際しては、その都度遅延なく、電子署名とタイムスタンプを付与することが義務付けられています。さらに、これまで蓄積した紙カルテの電子化については、さらに厳しい条件が課せられます。実施前に実施計画書を立て、患者からの同意を得ること、外部の厳格な監査を受けることが必須です。
カルテの保管期限は?
紙カルテなどの保管期間は、5年間という定めがあります。
しかし、5年間以上たった紙カルテの破棄や、スキャンして電子化した後に残ってしまった紙媒体の取り扱いなど、疑問に思うことも多いでしょう。
ここでは、紙カルテの保管に関する法律とともに、保管期限を過ぎた場合や、スキャン後紙カルテの取り扱いについて解説していきます。
紙カルテなどの保管に関する法律
診療録(カルテ)の保管期間は、医師法によって5年間と義務付けられています。ただし、医師法にはいつから5年間なのかということが明記されていません。
保管期間の開始の起点については、「保険医療機関及び保険医療担当規則第9条」にて、一連の診療が完結した日から5年間の保管、という内容で義務付けられています。つまり治療が継続している間は、この5年の中にはカウントされません。
また、紙カルテ以外の薬の処方箋、透析記録、レントゲンなどの検査写真などは、3年間の保存義務があります。
これに違反すると、50万円以下の罰金が科せられることも定められています。
また、新鮮凍結人血漿・人免疫グロブリンなどの特定生物由来製品については、20年間の保管期間が定められています。これは、感染症などの問題が発生した場合への原因究明などの対策のためです。
保管期間を守れば破棄しても良い?
「医師法」や「保険医療機関及び保険医療担当規則第9条」の観点から考えると、保管期間を守れば破棄して良いという解釈になるでしょう。
ただし、担当の患者が薬害問題などで国の給付を受け取る場合などには、医療機関のカルテ保存期間が過ぎても必要になることがあります。
また、医療事故や医療過誤が発生した場合にも、カルテの情報は非常に重要です。民事上の損害賠償請求権の時効が20年となっていますので、手元に紙カルテなどの治療の記録が残っていないと不利になるということを忘れてはいけません。
スキャン後の紙カルテは破棄しても良い?
紙カルテをスキャンすることで電子データとなった情報は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に準じ、電子署名・タイムスタンプを付与することによって、原本性を保持することができます。
このため、スキャン後の紙カルテは破棄しても良いことになります。
紙カルテには、患者さんの重要な個人情報の多くが含まれています。破棄をする場合は慎重な取り扱いが必要です。
廃棄の方法は、焼却、シュレッダー、溶解などの方法があります。一般的には専門の機密文書処理事業者に依頼することがほとんどです。
機密文書処理業者を選定する際には、同一業者内ですべての処理工程が終了することや、ISMS認証取得しているかが、セキュリティ体制を担保するために重要です。
電子カルテの導入で保管方法の悩みを解決できる
ここまで、紙カルテの整理や保管について説明してきました。開院当初の、新規患者が多い時期には、紙カルテの管理に悩まされることはあまりないかもしれません。
ところが、長く経営を続けていくにしたがって、カルテの保存方法には手間も費用もかかってしまうでしょう。
電子カルテは初期投資、ランニングコストが必要にはなりますが、電子データとしてすべての情報をサーバーで管理できます。保管場所や保管の方法にも手間がかからず、カルテ管理に関する悩みの解決に期待できます。
サーバー管理なのでカルテ棚などが必要ない
電子カルテでは、これまで紙ベースだったカルテの情報を、電子情報として一括で管理できます。
電子カルテには2種類あり、院内にサーバーを設置するオンプレミス型。そして、もう1つは、インターネットを通じて電子カルテベンダーが管理するサーバーを使用するクラウド型です。
どちらのタイプの電子カルテでも、サーバーに電子情報を管理できるため、紙カルテのようにカルテ棚は一切必要ありません。
診療録だけでなく、処方箋や検査データ、画像などの情報もサーバーに保存が可能なため、カルテ保存についての物理的な問題が解決されるでしょう。
バックアップや破棄も簡単
近年、地震や豪雨による災害によって、医療施設も甚大な被害を受けるケースが少なくありません。紙カルテは、保管場所にもよりますが、最悪の場合は復旧が困難なこともあるでしょう。院内にサーバーを設置しているオンプレミス型の場合は、データはサーバー内に存在します。サーバーがダメージを受ければ、情報を失う可能性も。
クラウド型の電子カルテでは、院内のパソコンやタブレットが破損したとしても、データはクラウド上に残っています。また、クラウドに保存される情報はすべて自動的にバックアップされています。
情報の破棄については、電子カルテも安全性を確保することが重要です。厚生労働省も、事前に廃棄プログラムなど、手順を明確にするべきとしています。破棄自体は紙カルテと同様、安全性を意識することが求められますが、紙カルテの手続きに比べると容易と言えるかもしれません。
画像なども一緒に保管しやすい
紙カルテの場合は、処方箋、検査データ、画像の保存も紙ベースです。特にレントゲンのテータなど、カルテサイズと異なるものについては、管理の場所がばらばらになってしまいがちです。診療・治療においては、画像データを比較して判断することが重要なため、
画面上で前回の画像データと、最新の画像データを並べて確認することができる電子カルテであれば、
わざわざ該当するレントゲンフィルムを探しだし、必ずしもシャウカステンにかざす必要もなくなり診察時の手間も省けるでしょう。検査データも同様です。
電子カルテを導入する際の注意点
電子カルテを導入する場合には、いくつか注意点があります。
一番は患者さんのデータを守ることです。納得できるセキュリティ対策が取られているかの確認は重要です。また、規模や診療の性質に合わせた電子カルテのシステムを選び、導入や運用に必要な費用を必ず見積もりしてもらう必要があります。
紙カルテ運用から、電子カルテへの移行を考える場合には、移行についてスタッフの理解を得ること、スタッフに電子カルテについての教育などが必須です。
データの保全・セキュリティ対策について確認する
患者さんの個人情報を守ることは、紙カルテにおいても電子カルテにおいても重要です。
クラウド型の場合はインターネットを使用したクラウド上へのデータ保存であるため、セキュリティに心配を持つ人もいるでしょう。
実はクラウドのサーバー上では、医療記録がそのまま保存されているわけではなく、外部からは判読できないような暗号化が施されています。
加えて、外部からはアクセスできないよう、厳重なセキュリティによって保護されています。
電子カルテを導入する際は、カルテのデータの保護への対策について、確認したうえで導入するシステムを検討しましょう。
運用に必要な費用は必ず見積もり比較をする
電子カルテにはオンプレミス型とクラウド型がありますが、この2つは運用にかかるコストに大きな違いがあります。
オンプレミス型では、サーバーなどの情報システムを施設内に設置する必要があります。このため、初期費用は500万前後と高額です。さらに5年に1度、システムの更新が行われ、初期費用と同等の金額が必要です。
一方、クラウド型は、サーバーはクラウド上なので、初期費用は初期費用は10万円程度から利用可能です。オプションを付けた場合も数十万円程度に抑えることができます。月額の支払いは数万円で収まります。さらに、システムの更新などの費用は掛からないため、長期的に見ても低コストと言えます。
同じ型の電子カルテでも、メーカーによって特性や費用は異なるので、見積もりを依頼し、比較することが大切です。
スタッフに対する研修を行う
長い間、紙カルテで運用をしてきたクリニックなどでは、スタッフも紙カルテで業務をすることに慣れています。紙カルテは管理上ではデメリットがあるように見えても、スタッフにとっては使いやすいと感じるものかもしれません。
このため電子カルテを導入する際には事前に研修を行い、電子カルテの操作ができるようサポートする必要があります。
また、パソコン自体に苦手意識のある人や、あまり触れる機会がない人もいます。システムの操作だけでなく、最低限のパソコン操作のスキルを身につけてもらえるようなサポート体制も考慮するべきでしょう。
自由診療クリニックのカルテ整理ならMEDIBASEへ
いま、開業しているクリニックが自由診療であれば、「MEDIBASE」がおすすめです。MEDIBASEは自由診療に特化したクラウド型の電子カルテ。低コストでの導入、運用が可能で、施術の役務管理も簡単に行うことができるため、自由診療には有益なシステムです。
特に画面デザインは紙カルテと同様に操作しやすく、長年紙カルテを使用してきたスタッフでも使いやすいようになっています。
クラウド型電子カルテを利用することによって、情報管理の安全性や業務効率が良くなり、患者さんへの質の高い診療の提供につながります。
現在のカルテ整理や診療の特徴を確認し、自院に適したクラウド型電子カルテの導入を検討をおすすめします。