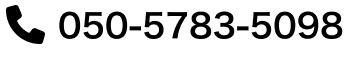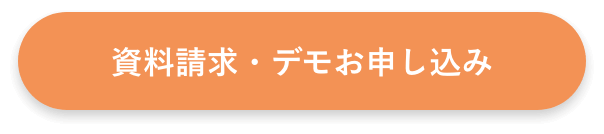【2022年最新】電子カルテに利用できる補助金はある?
電子カルテを検討しているけれど、少しでも費用を抑えたいと考えているクリニック・病院の経営者もいらっしゃるでしょう。
実は、電子カルテの導入にも、利用できる補助金がいくつかあるのをご存じでしょうか。この記事では、利用できる補助金事業をいくつか紹介しています。IT導入補助金については、申請方法など手続き関連にも触れています。
最後には、費用を抑えることができるクラウド型の電子カルテをご紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただき、電子カルテ導入時の参考にしてください。
目次
電子カルテの導入で利用できる補助金は?
電子カルテを導入することで、業務の効率化や感染防止対策に効果を発揮し、最終的には患者さんに対する医療・ケアの質を高めることにもつなげられるでしょう。
厚生労働省でも国民の健康確保のためのデータヘルス改革が推進されており、電子カルテは補助金制度の対象になっているのです。
ここでは、どのような補助金制度があるのか解説していきます。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などに対して、業務の効率化や売り上げアップをサポートするために、ITツールを導入する経費を一部補助するものです。
2017年から、経済産業省と独立行政法人中小企業基盤整備機構のもとに実施されています。
IT導入補助金2022では、2021年から類型の一部が変わっています。補助金の通所枠(A類型・B類型)はこれまでと同様の類型。これに加え、「デジタル化基盤導入類型」「複数社連携IT導入類型」が設定されています。
東京都病院診療情報デジタル推進事業
東京都病院診療情報デジタル推進事業は、電子カルテの病院への導入を支援することで、医療連携ネットワークの構築を推進するための補助事業です。
対象者は東京都内の200床未満の病院を開設するもの、とされています。ただし、地方公共団体や特的独立行政法人は対象外など、条件があるので確認が必要です。
補助対象の経費は、「電子カルテシステムの整備」「病院内に設置する医療情報システム」。
事業実施の条件として、1年以内に地域医療連携ネットワークへの参画と、事業の効果検証のための東京都への協力が求められます。
交付は事業計画書の内容の審査によって決定されますが、申請しても採択されない場合もあることを知っておく必要があるでしょう。
オンライン資格確認関係補助金
オンライン資格確認は、保険資格の確認がオンラインでできる仕組みです。マイナンバーカードの情報をカードリーダーで読み込み、暗証番号か顔認証を同時に行うことで、最新の保険資格を自動で取得することができるのです。保険証でも最小限の入力のみで、情報を取得できるので受付業務を効率化できます。
このオンライン資格確認を行うためには、顔認証付きのカードリーダーが必要です。オンライン資格確認関係補助金では、これらの設置に関する費用の補助を受けることができます。
なお、厚生労働省と社会保険診療報酬支払基金のもと実施される補助金です。
医療情報化支援基金(電子カルテ標準化に関する補助金)※未発表
日本は電子カルテの標準化を目指し、電子カルテの普及率を向上させること、マイナンバーカードによる健康情報の共有の推進を図っています。
しかし、厚生労働省の医療施設調査によると、2017年時点の電子カルテ普及率は一般病院の病院規模別では、400床以上で85.4%、200~399床で64.9%、200床未満で37.0%。病院規模が小さいほど普及率は低い傾向にあるのが現実です。
このため、政府は電子カルテの標準化と普及を目指し、導入に必要な費用の補助金を交付するため、「医療情報化支援基金」を2019年に設立しています。
今後も、状況次第で新たな補助金が現れる可能性があるため、常に情報をチェックしておくと良いでしょう。
IT導入補助金の概要
IT導入補助金は、経済産業省と独立行政法人中小企業基盤整備機構の監督のもと実施されています。中小企業や小規模事業者が、自社の課題を解決し生産性を高めることを目的としたITツール導入の際の経費を一部補助してくれます。医療機関においても同様で、電子カルテなどのシステム導入時の補助金を受けることが可能です。ただし、申請すれば必ず受給できるわけではありません。審査を通過する必要があり、採択率は50%とも言われていますので、採択されなかった場合も想定した電子カルテの導入を検討する必要がありそうです。
※「IT導入補助金2022年」について、記事制作時点(2022年3月末)では制度設計段階にあります。公募公開になるまでは変更となる可能性もあるので、ご注意ください。
IT導入補助金の類型ポイントは?
令和3年度の補正予算における、IT導入補助金の類型は以下のようになっています。
- 通常枠A類型
- 通常枠B類型
- デジタル化基盤導入類型
- 複数社連携IT導入類型
通常枠(A・B類型)は、IT導入補助金が措置された令和元年から変わらない類型で、生産性や経営力を高めることを目的としたITツールの導入に対して申請できます。
令和3年度の補正予算から制定された「デジタル化基盤導入類型」は会計ソフトや決済ソフトなどのソフトウェア、PC・タブレットなどの端末の導入費用を支援。
「複数社連携IT導入類型」では、複数の中小・小規模事業者が連携してITツール・ハードウェアを導入し、地域のデジタル化や生産性の向上を図る際の支援が行われます。
電子カルテも対象? IT導入補助対象経費とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が、業務を効率化し生産性を向上させるために、ITツールを導入する経費を一部補助するものです。
電子カルテもITツールの1つであり、IT導入補助金を活用することができます。
通常枠(A・B類型)では、労働生産性の向上に資するITツールであるソフトウェア費、クラウド利用料(最大1年分補助)、導入関連費等が補助対象です。
「デジタル化基盤導入類型」では、補助対象が会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトなどのソフトウェア、クラウド利用料・導入関連費に特化しています。「複数社連携IT導入類型」では、さらに消費動向分析システム、経営分析システム、生体認証決済システムなどが補助対象となります。
補助対象事業者とは?
事業の申請となる対象は、中小企業と小規模自営業者です。
医療機関の場合は、「医療法人の場合は従業員300人以下」が中小企業の枠に該当します。そして、「個人事業主の場合は従業員20人以下」が小規模事業者に枠組みされることになります。
また、他の補助金との併用ができないこともあるので注意が必要です。例えば国の管轄下にある他の補助金や助成金を受給している場合は、同じ事業や費目でIT導入補助金を併用する申請はできません。
2022年の変更点は?
2022年度には、新たにデジタル化基盤導入枠が制定されました。その中でも次の4点が大きな変更点です。
- 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化し、補助率を引き上げ
- クラウド利用料を2年分まとめて補助
- PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加
- 複数社連携IT導入類型の創設
多くのITツールがクラウド化していることを考慮して、クラウド利用料の補助が2年分になるなど、現状に合わせて補助を特化し拡充していることがわかります。
デジタル化基盤導入枠が該当すれば、クラウド型の電子カルテを病院に導入する場合には、クラウド利用料の補助は効果的に活用したい補助金の1つです。
IT導入補助金の申請方法

申請方法は決まった流れ通りに進めていかなくてはなりません。提出書類の差し替えなどもできないため、一発勝負に近い申請です。一連の流れを確認したうえで、慎重に準備を進める必要があります。
また、申請を始める前には以下のような申請条件が合っているかどうかの確認が必要です。
- 「医療法人の場合は従業員300人以下」「個人事業主の場合は従業員20人以下」の医療機関であること
- 交付申請時点で日本国内に登録がある個人・法人であり国内で事業をしていること
- 交付を申請する直近の月で、最低賃金が法令上の地域別最低賃金を満たしていること
この条件を満たしたうえで、申請を開始していきます。
申請の流れ
申請は、IT導入補助金のページから、オンラインで行うことができます。
申請の流れは以下のようになります。
- 公募要領を確認
- 必要なITツールとIT導入支援事業者の選定
- 交付申請のページへのログインのため、gBizIDのプライムアカウントを取得
- 「SECURITY ACTION」宣言を行う(独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施)
- IT導入支援事業者と事業計画を策定し、交付申請する
- 交付が決定したら、ITツールの発注・契約・支払いを行い、事業を開始
- 補助金交付手続き
- 事業実施効果報告
申請においては、IT導入支援事業者と必要書類を共同作成するなど、連携を取る必要があります。
申請に必要な書類
交付申請時に必要な書類は、法人での申請、個人事業主の申請で異なります。
|
|
交付申請時の必要書類 |
|
法人 (医療法人の場合は従業員300人以下) |
・履歴事項全部証明書 ・法人税の納税証明書(その1またその2) |
|
個人事業主 (従業員20人以下) |
・運転免許証または運転経歴証明書または住民票 ・所得税の納税証明書(その1その2) ・所得税確定申告書B |
出典:交付申請の手引き
事務局へ提出した申請の訂正や、書類の差し替えはできません。さらに、採否の発表まで取り下げもできないため、必要書類の提出時は十分確認をして申請する必要があります。
交付までにかかる期間
過去のIT導入補助金の申請から交付までのスケジュールを見てみると、申請から交付までの期間は4~5カ月が目安になりそうです。
|
申請 |
かかる期間 |
|
交付申請期間 |
約2週間 |
|
申請から交付決定日 |
約2週間~1カ月間 |
|
事業実施期間(事業実績報告期間) |
約6カ月間 |
補助金交付の目安は、事業実績報告から約2カ月が目安になっています。
例えば、6月末に交付が決定した場合、7月末までにITツールの導入と事業実施報告を完了させれば、9月末~10月の間に補助金が交付されることになります。
なお、交付決定を受ける前に、契約・発注・支払いを行った場合は、補助金の交付は受けることができません。このため、IT事業の開始は必ず交付決定を受けてからの開始が必要になります。
交付にはかなりの時間を要すことを念頭に置いて、IT導入補助金の申請を行う必要があるでしょう。
IT導入補助金のデメリット

IT導入補助金は、「規定に従えば、原則返済不要な補助金である」「費用を抑えてITツールを導入できる」などメリットも多いですが、いくつかのデメリットも避けられません。
- 補助金の給付が後払いであること
- 必要書類の準備が大変
- 登録されているITツールに限定されること
- 必ず採択されるわけではないこと
- 事業実績報告を一定の期間し続ける必要があること
ここからは、一部のデメリットについて解説していきます。
選べる電子カルテが限られている
IT導入補助金を申請する場合、IT導入支援事業者及びITツールは、事前に登録されているものから選ばなければなりません。このため、選べる電子カルテは限られてしまいます。使いたいと思った電子カルテが登録されているとは限らず、事前に確認をしておく必要があります。
登録されている事業者やツールを確認したい場合には、IT導入補助金の公式サイトから検索することも可能です。各年度で登録内容はかわるので、年度を確認してチェックします。ただし、2022年分は更新されていないため(2022年3月時点)、前年度分を参考程度に見ておくと良いでしょう。
交付までに時間がかかる
IT導入補助金は、申請してから交付までに、半年程度の時間がかかってしまいます。また、過去の申請状況を確認すると、1年間に1次募集と2次募集の2回しかないため、申請・交付のタイミングを考えITツールの導入を計画しなければなりません。病院の開業や経営のスケジュールにも合わせ、計画的な準備が必要です。かといって、必ずしも採択されないため、不安定さが否めません。
また、開業準備に間に合わないからと、交付が決定する前に、発注・契約・支払いをしてしまうと、補助金の対象外になってしまうので、気を付けなくてはなりません。
さらに、実際に補助金をもらえるまでは、一旦自費で全額分を支払い、電子カルテを用いた事業を開始しなければなりません。
費用を抑えて電子カルテを導入するならクラウド型がおすすめ
補助金は、他の補助金と併用ができないことがあります。その場合は、すでに国が管轄している他の補助金や助成金をすでに受けている場合は、IT導入補助金を併用することができません。
また、補助金制度は倍率が高いため、申請をしても通らないケースもあります。
すでに他の補助金を利用している、申請できる条件に当てはまらないという場合には、
費用を抑えやすいクラウド型の電子カルテがおすすめです。
電子カルテには、オンプレミス型とクラウド型の2種類があります。オンプレミス型が初期費用500万円前後かかるのに比べ、クラウド型の電子カルテは数万円が相場です。また、月額の費用も数万円とランニングコストも抑えることができます。さらにオンプレミス型では5年ほどでシステムの更新があり、初期費用と同等の費用が必要です。クラウド型にはシステム更新もなく、長期的にも低コストで運用が可能な電子カルテです。小規模な病院にはフィットする電子カルテと言えるでしょう。
自由診療クリニックのクラウド型電子カルテなら「MEDIBASE」
MEDIBASEは自由診療に特化した、クラウド型の電子カルテです。使用するパソコンの台数、利用者の人数に制限はなく、一医院あたり月額39,800円と低コストで利用ができます。
直感的に操作しやすい画面デザインは、紙カルテのような感覚での入力を可能にします。
さらに、インターネット診療予約の機能もあり、煩雑になりがちな予約管理の業務も効率化を図れます。複数回の施術の診療コースの設定ができるため、自由診療ならではの役務管理も簡単にできるようになります。
自由診療のクリニックで電子カルテの導入をご計画の場合は、ぜひMEDIBASEをご検討ください。