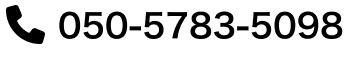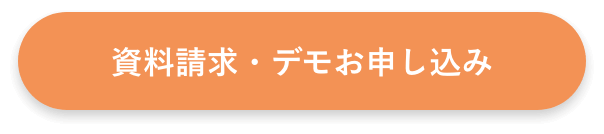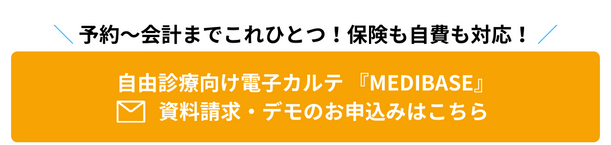精神科・心療内科におすすめの電子カルテとは?選定ポイントやメリットをご紹介
激化する競争社会の中で、多くの人がストレスを抱えています。実際に精神科や心療内科を受診する患者が年々増加。予約は数週間から数か月先までいっぱいという状況で、病院の予約管理も大きな負担です。疾患の性質上、受診歴の長い患者さんも多く膨大な紙カルテを保管することも課題の1つでしょう。
この記事では、精神科・心療内科が抱える課題の解決に役立つ、電子カルテの選定ポイントやメリットを解説しています。記事の最後にはおすすめのクラウド型電子カルテをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
精神科・心療内科の病院・クリニックの課題
現代社会は科学技術の高度化に伴い、経済的に豊かになりました。生活は快適になっている一方、激しくなる競争社会の中で、人々は人間関係などの悩みにより多くのストレスを抱えています。実際に精神疾患を有する外来患者は平成26年361.1万人から平成29年には389.1万人と年々増加しているのです。現在はコロナ感染症の影響で、さらに患者が増加していることが推察されます。精神科・診療内科においては、増加する患者さんへの対応が、今後も求められるでしょう。
参考:厚生労働省 個別事項(その3)
電子カルテは患者さんと目を合わせづらい
精神科や心療内科領域を受診する患者さんは、頭痛や吐き気、腹痛、めまい、不眠といった様々な不調を持っています。診察をする中で、体調不良の原因を辿っていくと、ストレスが密接に関係しているケースがあるのです。このため、精神科・心療内科の診察では、まずは「患者さんの話を聞く」ことから始まります。紙カルテであれば、患者と向き合いながら記載しやすいでしょう。しかし、電子カルテの場合は画面を見ながらタイピングしたり、見たい情報や書きたいページを探すためのクリック数も増えたりしがちで、患者さんと目を合わせづらいといったデメリットがあります。
患者さんの待ち時間が長い
身体に現れた不調の原因を明らかにするためには、身体診察や血液検査といった情報収集とアセスメントはもちろん、医療面接を綿密に行うことが重要です。さらに、心理テストなどから本人の社会的背景や性格、行動パターンの分析も行います。身体的、精神的、社会的な面から全人的な把握をすることが求められるのです。
このため、特に初診や通院期間の浅い患者さんの場合には、1人当たりの診察時間が長くなるケースが多くなりがちです。この結果、来院している患者さんの待ち時間が長くなるという問題が起きてしまいます。
長く付き合う患者さんが多く、管理が大変
精神疾患も心身症も、治療期間が長くなるケースが多いです。
精神疾患の場合は、統合失調症、うつ病、不安障害などの疾患が治療対象であり、これらの疾患は軽快しても、再度悪化するような場合もあります。症状の再発を予防する必要があり、長期的な治療が必要になるケースも少なくありません。
心療内科の主な対象は、心身症。心身症はストレスや不安によって、自立神経失調症や緊張性頭痛などの症状を呈します。治療は身体に起きている症状だけでなく、精神面の治療が重要に。ストレスの軽減とともに、心理的な治療が必要なため長期的な治療が必要と言われています。
このように精神科や心療内科では、長期的に関わる患者さんが多いため、その情報の管理には場所やコスト、手間がかかってしまいがちです。
予約の調整が難しい
精神科や心療内科は、余裕を持った診察時間を確保して医療面接を行います。このため、当日予約ができるクリニックは少ないのが実情です。受診患者の数が増えているため、数週間、場合によっては数か月先まで予約が埋まってしまう事も珍しくありません。電話予約での受付では、数か月先の予約管理を間違えないように調整する必要もあるのです。
医師の学会や会議の参加によるイレギュラーな休業日もあるため、正確なスケジュール確認や調整が必要になります。
精神科・心療内科が電子カルテを導入するメリット

毎日の受診者数が多い精神科や心療内科では、電子カルテを使って記録やデータ管理を行うことで、事務的な作業を効率化することが可能です。
一方で、電子カルテは、患者さんと目を合わせづらいといったデメリットを感じるかもしれません。しかし電子カルテのシステムの特徴を理解して、使い方を工夫することで患者さんとの対話の障害になることなく、スムーズに運用することも可能です。
電子カルテ、紙カルテのどちらを使うかでなく、患者さんとの対話を大事にする姿勢が大切になってくるでしょう。
データ共有が容易で、患者さんを待たせない
紙カルテの場合は1人が記録、閲覧している場合は、他のスタッフは記録閲覧ができません。しかし電子カルテであれば、複数のスタッフが1人の患者さんの情報を同時に閲覧、記録することが可能です。
さらにタイムリーに記録を行うことで、医師、看護師、臨床心理士やカウンセラーが同時に情報共有することができます。各スタッフが得た情報をリアルタイムに記録して共有できることは、情報の伝達漏れや、重複した情報収集を防ぎ、患者さんへの負担や待ち時間を軽減できるでしょう。
文書作成の手間を削減できる
精神科領域では、精神保健福祉法により定められた、「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」入院制度があり、入院時、退院時など、定められた文書の作成が必要になります。精神科領域では、その他にも特有の文書が多く作成に手間がかかります。
電子カルテであれば、フォーマットを利用して効率的に記載が可能になります。カルテ内の情報の再利用が簡単にできるため、転記ミスなどの間違いを避けることできます。さらに、膨大な量になりがちな文書の保管も電子カルテ内で一括管理できるため、ファイリングの手間もなくなります。
参考:厚生労働省 精神科の入院制度について
予約管理・会計管理も容易に
予約は数週間、数か月先まで埋まってしまう事も珍しくない精神科・心療内科。受付業務と並行しながらの電話予約対応で、数か月先の予約管理を間違えないように調節するのは、スタッフの精神的負担も大きいでしょう。
電子カルテには、予約受付機能を連携できるものや、最初から機能が搭載されたものがあります。患者さん自身がインターネット上で予約をすれば、カルテ上で予約管理を容易に行うことが可能です。
さらにレセプトコンピューターと連携可能な電子カルテもあるため、会計管理も簡単に行うことができます。
紙カルテをスキャンしてデータ管理できる
毎日の受診者数が多い上、1人当たりの受診歴も長い精神科・心療内科では、患者情報やカルテのデータが膨大であるクリニックが多いでしょう。紙カルテから電子カルテに移行を考えるにあたり、過去の紙カルテの保管方法に頭を悩ませている場合もあるかもしれません。
この場合は、厚生労働省が通達している「診療録などをスキャンなどにより電子化して保存する場合について」に準じて、紙カルテをスキャンし電子化して保存することも可能です。療養期間の長い患者さんの膨大な紙カルテも、電子化すれば保存場所に困りません。
ただし、紙媒体を破棄する場合は、個人識別不可能な状態にすることが必須です。また、これら一連の流れは患者さんの同意の元、成立します。
参考:厚生労働省 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について
精神科・心療内科で電子カルテを導入するデメリットはある?
小規模な病院であることが多い精神科・心療内科においては、コストの問題が電子カルテ導入における大きなデメリットでしょう。
サーバーを院内に設置するオンプレミス型電子カルテでは、諸費費用は約500万円程度。5年ごとに必要なシステム更新には、初期費用と同等の費用がかかります。さらに保守費用などのランニングコストも必要です。長期的にも高額な費用がかかり、大きな負担になることが推察されます。また、カウンセリングなど自由診療を扱う精神科・心療内科では、自由診療に対応する電子カルテが少ないこともデメリットといえます。
精神科・心療内科で電子カルテを導入する際のポイント

多くの精神科・心療内科領域では、カウンセラーや臨床心理士による、自由診療のカウンセリングを取り入れているクリニックも多いでしょう。このため、電子カルテは自由診療に対応したものが望ましいと言えます。また、低コストで抑えられるクラウド型の電子カルテで、自院が提供する医療にフィットしたサービスを選定することも大切です。
精神科・心療内科に対応できるものを選ぶ
カウンセラーや臨床心理士によるカウンセリングは自由診療での扱いになります。レセプトコンピューター(レセコン)と連携ができ、自由診療にも対応した電子カルテであれば、保険医療、自由診療の請求管理を一括管理することが可能です。請求管理において医療事務スタッフの負担の軽減につなげることができます。
また、カウンセリングには様々な手法があり、個別に合わせた方法が選択され複数回の通院が必要になることがほとんどです。個別のカウンセリングスケジュールを管理しやすい電子カルテを選ぶと良いでしょう。
クラウド型ならコストをおさえて導入できる
小規模な病院や診療所には、低コストで導入できるクラウド型の電子カルテがおすすめです。一般的に初期費用は数十万円程度に抑えることが可能です。さらに、月にかかる費用は数万円と、ランニングコストを抑えることも可能。導入する際に、「患者情報の移行作業」や「操作説明」などのオプションを付けても、初期費用は10万円~30万円ほどに収まることが一般的です。
クラウド型電子カルテは、長期的に見ても低コストであり、精神科・心療内科にも多い小規模病院向けのサービスと言えます。
手書き文字を利用できる電子カルテを選ぶ
精神科においては、患者さんがどのような状態だったかなど、カルテの選択項目だけでは記載できない細かな情報も重要になってきます。
タイピングで電子カルテに記載するとなると、患者さんよりもカルテに記載をしている時間が長くなってしまう懸念点もありますので、紙カルテのように手書き文字でも記録を残せる電子カルテを選ぶのも1つの手です。
精神科・心療内科におすすめの電子カルテ「MEDIBASE」
診療所やクリニックの形態が多い精神科・心療内科には、自由診療に特化したクラウド型電子カルテの「MEDIBASE」がおすすめです。自由診療に特化した設計かつクラウド型電子カルテなので低いコストで導入することが出来ます。月額料金は39,800円で、使用するパソコンの台数や利用人数が何人でも1院当たりの金額は変わりません。システムの更新もないので、ランニングコストも抑えることができます。
予約管理から会計管理までワンストップ
MEDEIBASEではインターネット診療予約システムを連携させることが可能です。患者さん自身がインターネット上で予約を行うことができ、予約情報を電子カルテで一括管理ができます。加えて、患者さんが来院した際の受付は、タッチパネルの操作で完了。カルテ操作や受付業務を軽減し、患者さんへの対応もスムーズに進むでしょう。
自由診療に特化している
MEDIBASEの電子カルテは、国内でも希少な自由診療に特化した電子カルテです。
臨床心理士やカウンセラーによって行われるカウンセリングは自由診療なので、精神科・心療内科ではフィットしやすい電子カルテと言えます。
また、カウンセリングは、相談者自身が自分で悩みや困りごとの解決策を導き出せるように導くプロセスであり、複数回の通院が必要です。MEDIBASEでは、診療コース管理機能も搭載しており、自院の治療に併せて自由に組み立てができます。患者の個別に合わせたカウンセリングコースの設定が可能です。
記入しやすく、画面を見続ける必要がない
一般的な電子カルテの画面は、1つのメイン画面の上に、別の小さい画面を開いたうえで入力するシステムになっています。MEDIBASEでは小さな画面は開かないため、メインの情報画面が隠れることがありません。さらに、MEDEIBASEでは検索ページが搭載されており、閲覧したいページや記録したいページに、直ぐにたどり着くことが可能。クリック数が少ないため、電子カルテの画面を見続ける必要がありません。
患者さんとの対話にも邪魔にならず、紙カルテのような感覚でスムーズに記録ができることで、業務を効率化できるでしょう。提供する医療やケアの質向上をねらえます。
まとめ
ストレス社会と言われる現在、精神科や心療内科を受診する人が年々増加しています。さらに現在では、コロナ感染症の影響でさらに増加していくことが推察されます。精神科や心療内科の担う役割はますます大きくなるでしょう。
カルテ管理を効率化することは、医療スタッフの負担を軽減するだけでなく、最終的には患者さんへ質の高い医療やケアを提供するためにも重要です。
ぜひ、自院におけるカルテに関する課題を明確にして、電子カルテ導入をご検討ください。