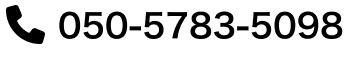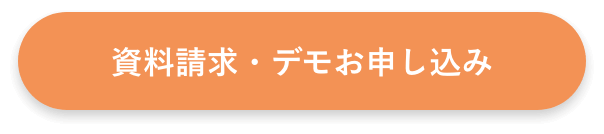歯科におすすめの電子カルテとは?選定ポイントやメリットをご紹介
日本の歯科診診療所は、コンビニ店舗数を上回るほどの多さです。このため、歯科衛生士や歯科助手といった人員の確保が難しい状況があります。一方、日本において健康寿命を延ばすための施策が推進され、歯周予防といった、歯科の担う役割が大きくなっています。この結果、歯科受診の患者さんが多くなり待ち時間が長くなるなどの影響が出ている状況です。
この記事では、歯科の抱える課題の解決に役立つ、電子カルテの選定ポイントやメリットを解説します。記事の最後には歯科向けの、自由診療に特化したクラウド型電子カルテをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
歯科の病院・クリニックの課題
厚生労働省の医療施設調査によると、日本の歯科診療所はなだらかに増え続けてきました。令和3年1月時点では、全国68,024施設と前年から64施設減ではあるものの、全国57,999件(2020年度)のコンビニ店舗数を上回る数です。
その影響もあり、歯科衛生士をはじめとした人員確保が困難なため、患者さんの待ち時間が長くなるといった課題が表面化しています。
また全国の歯科では、電子カルテの導入は57.3%と半数を超えているものの、普及率高いとは言えない状況で、業務の効率化を検討するうえでも電子カルテ導入の検討は重要な事項と言えるでしょう。
人材の確保が難しい
日本では健康寿命を延ばすための予防医療を推進しており、歯科が重要な役割を担っています。特に歯周病の予防は、全身の健康維持やフレイル予防による介護への対策など、多様なニーズがあるのです。また、生涯をできる限り自分の歯で過ごしたい、より美しく幸せでありたいという審美歯科へのニーズも高まっています。
このようなニーズに対応するためには、歯科助手・歯科衛生士の確保が必要です。しかし、歯科医院・クリニックの数が増えている現在、人材確保は多くの病院を悩ませる課題の1つです。
患者さんの待ち時間が長い
1989年に厚生省(当時)と日本歯科医師会によって8020運動が推進されてきました。2016年時点で、20歳以上で過去1年に歯科検診を受けた者の割合は52.9%と年々増加しています。そして、歯科受診患者のうち、65歳以上の高齢者が45.2%と、こちらも年を追うごとに増加している状況です。
歯科医院やクリニックの施設数は多いものの、受診者に対して医療スタッフが少ないため、患者さんの待ち時間が長くなってしまうという状況が起きていると考えられます。
カルテの共有に手間がかかる
歯科における電子カルテの普及率は57.3%とそれほど多くないため、導入していない歯科は紙カルテの使用がほとんどと考えられます。紙カルテの場合、1人のスタッフが閲覧・記録をしているときには、他のスタッフは何もできません。情報共有するためには、その時にしている作業の手を止めて、カルテがあるところまでの移動が必要なため、手間と時間がかかります。少しの時間だとしても、多くの患者さんを抱える歯科であれば、大きなタイムロスになっているでしょう。
画像管理に手間がかかる
歯科医院では、むし歯の場合にもレントゲン撮影が必要になります。さらに、歯科用CTの撮影を行う歯科もあるため、画像のデータの管理が重要です。紙カルテの場合、レントゲンのフィルムを紙カルテと同様に保存し、CTの画像はそのデータと紙カルテと連携させて整理しなければならず、時間と手間がかかってしまいます。
加えて、画像のデータは患者さんへの治療の説明のためにも必須の情報です。しかしながら、そのデータを見てもらうためには、画像を開けるコンピューターを患者さんの近くに移動させるか、印刷した物を持っていくかなど、スムーズな運用には課題があるでしょう。
歯科が電子カルテを導入するメリット

毎日多くの患者さんの診察と治療を行う歯科。効率的に記録を行える機能やシステムを搭載した電子カルテは、診療業務や経営管理において多くのメリットを与えてくれるでしょう。
電子カルテには、検査データや画像の保存も可能な機能を搭載した製品もあり、患者さんへのインフォームドコンセントの質を高めるためにも有益です。そして、記録が効率的になることで、スタッフは患者さんへのケア提供に時間をかけることが可能に。質の高いケア、信頼関係の構築にもつながるでしょう。
簡単にカルテ記載ができる
紙カルテの運用をしている病院では、紙カルテの自由度の高い使い勝手を好んで継続使用している場合もあります。
近年の電子カルテでは、記載しやすい画面デザイン、操作しやすいシステムを実現している製品も多くなっています。歯科では、上下の歯のどの部位にどのような治療を行ったのかを記録することは、治療を継続するうえで重要です。治療部位を絵で示し、補足の説明を記入できる機能がある電子カルテでは、簡単に記録に残すことができます。
文書作成の手間を削減できる
歯科領域では、保険医療を行う上で、必ず患者さんに提供しなければならない文書が複数あります。
下記に記すものはその一部です。
・歯科疾患管理料にかかる管理計画書(初回用)
患者さんの主訴に関する審査結果や治療方針の説明を記した文書
・歯科衛生士実施指導説明書
歯科衛生士が実施した歯周検査結果や指導内容に関する説明を記した文書
・新義歯指導説明書
新しく制作した義歯の取り扱いや保管・清掃方法などの説明を記した文書
電子カルテであれば、これらをフォーマットにして準備しておくことが可能です。フォーマットを使用して記録ができるため、時間短縮にもなり簡単に作成できます。
予約管理・会計管理も容易に
電子カルテの製品によっては、予約システムとの連携が可能な製品があります。患者さん自身が、インターネット上で都合の良い日を登録すれば、予約が完了します。この機能によって医療事務のスタッフの予約の電話対応、予約管理の業務が軽減できる上、予約の記載漏れといった人為的なミスも予防できます。
また、電子カルテはレセプトコンピューター(レセコン)との連携が可能であることがほとんどで、請求・診療報酬情報の管理や会計管理も容易に行うことができるでしょう。
歯科で電子カルテを導入するデメリットはある?
歯科領域では、自由診療である審美歯科の治療を扱う病院があります。むし歯の治療でも使う素材によっては、自由診療の対象です。このため、自由診療対応の電子カルテの導入が望ましいでしょう。ところが、自由診療対応の電子カルテはオンプレミス型であることが多く、小規模病院であることが多い歯科にとっては、コストが大きな負担になるかもしれません。
病院内にサーバー設置の必要がある、オンプレミス型では、初期費用が500万円程。その後、リースが切れる5年ごとにシステム更新が必要で、更新費用として初期費用と同等の費用が必要です。保守費用などランニングコストも必要になることは、導入のデメリットになり得ます。
歯科で電子カルテを導入する際のポイント

歯科医院やクリニックの規模で電子カルテを導入する際には、初期費用やランニングコストを抑えられるものを選定することが重要です。さらに自由診療にも対応したシステムであれば、売上の管理もしやすくなるでしょう。
また、診療の面では、画像や文書の取り込みや記載が容易であれば、記録の時間を短縮でき効率的に業務を進めることが可能に。人員不足問題解決の一助にもなるでしょう。
また、診察内容の文章や、治療部位を絵で示すなど、自由度の高い記載が可能な電子カルテであれば、他のスタッフとの情報共有も行いやすくなります。
歯科に対応できるものを選ぶ
歯科医院やクリニックの規模では、導入しやすいコストの電子カルテを選定する必要があります。クラウド型電子カルテであれば、初期費用は数十万円であることがほとんどです。長期的にも手もシステムの更新などがなく、ランニングコストを抑えることができます。
また、歯科においては、治療を行う上で必ずと言っていいほど、レントゲン撮影が必要になります。CT撮影が必要な場合も。このため、画像の保管も簡単かつ確実に行うことができるような、電子カルテ導入が望ましいでしょう。
予約システムと一体型または連携ができるものを選ぶ
歯科は、受診者数の多い診療科でもあります。受付業務では、電話予約の対応のために、している業務の手を止めなければならない、といったこともあるでしょう。電子カルテが予約システムとの連携、または一体化しているものであれば、受付業務の効率化の効果が期待できます。また、予約状況もカルテ上で確認できるため、来院者の次回の予約についてもスムーズに調整することができるようになります。
電子カルテであれば、予約情報についてもスタッフ全員で共有することが可能で、受付に確認するといった細かいタイムロスも軽減できます。
自由診療に対応したものを選ぶ
歯科では自由診療の治療を扱っているため、自由診療対応の電子カルテを導入することが望ましいでしょう。自由診療対応であれば、受付の会計業務はわかりやすく、スタッフの業務負担を軽減できるため有益です。
レセプトコンピューターと連携できれば、通常の診療の診療報酬情報、請求情報も同時に管理することができます。
加えて、審美歯科ではホワイトニングなど数回のコースで行われるものも。このような治療コース設定の機能があれば役務管理もしやすいでしょう。
歯科におすすめの電子カルテ「MEDIBASE」
歯科医院・クリニックでは、自由診療に特化したクラウド型電子カルテ「MEDIBASE」がおすすめです。クラウド型なので低コストで導入可能であり、自由診療に特化した設計。1医院あたりの使用するパソコンの台数、利用者の人数は関係なく、月額利用料は変わりません。また、カルテの操作画面は直感的に操作できるデザインです。
長年紙カルテを使ってきた病院で、パソコン操作に苦手意識のあるスタッフがいても、レクチャーを受ければ、紙カルテの感覚でスムーズな運用が実現するでしょう。
画像管理機能を搭載
MEDIBASEでは、文書・画像ファイリングシステムを搭載しています。撮影したレントゲン、CTの画像データは、カルテ内に保存ができます。さらに、時系列で画像を2枚並べて表示したり、重ねて表示したりといった操作が可能で、前後の比較など患者さんへの説明もしやすくなります。審美歯科のように、時間や費用をかけて、美しさを追求する治療の場合には、治療前後の比較はインフォームドコンセント時には特に重要な情報です。患者さんが納得できるような治療を提供するためにも、画像管理機能を役立てることが出来るでしょう。
自由診療に特化している
MEDIBASEでは自由診療特化のクラウド型電子カルテを提供しています。診療コース管理機能も搭載しており、自院の治療に併せて自由に組み立て可能です。ホワイトニングといった審美歯科の治療コースで提供する、治療の役務管理もしやすいのが特徴です。コースの残数なども記録に残るため、治療の進行の把握にも役立ちます。
請求情報や診療報酬情報についても、クラウド上で同時に管理することが可能です。
記入しやすく、業務の効率化が可能
紙カルテのように、患者メモや受付メモを電子カルテ上に自由に記載できます。この機能があれば、その日の診療に関わるスタッフ全員でリアルタイムに情報共有が可能です。医師と歯科衛生士とのやり取りもよりスムーズになるでしょう。
また、多くの電子カルテは、1つのメイン画面の上に、別の小さい画面を開いたうえで入力する画面デザインです。MEDIBASEでは、この小さな画面は開かずメインの情報画面が隠れません。同じ画面でデータを確認しながら同時に入力できるため、入力ミスを予防できる上、業務を効率化できます。この直接編集機能は、特許を取得しております。
また、MEDIBASEでは検索ページがあるため、クリック数が少なくなり、業務の効率化につながるというメリットも。紙カルテのような使用感で、業務の効率化を目指せます。
歯科医院には電子カルテの導入をおすすめします
日本において、健康寿命を延ばすための施策には歯周病の予防といった、歯科領域の担う役割が大きくなっています。ところが、日本の歯科診療所の数が多くなる中、歯科衛生士や歯科助手といった人員の確保が難しいという課題が浮き彫りです。
カルテ管理を効率化することで、煩雑化した業務の改善を目指すことができ、人員不足の一助となるでしょう。
加えて、治療や診療、ケアに存分に時間をかけ、患者さんに質の高い医療やケアを提供することができるようになります。
ぜひ、自院における業務上の課題を明確にして、電子カルテ導入をご検討ください。